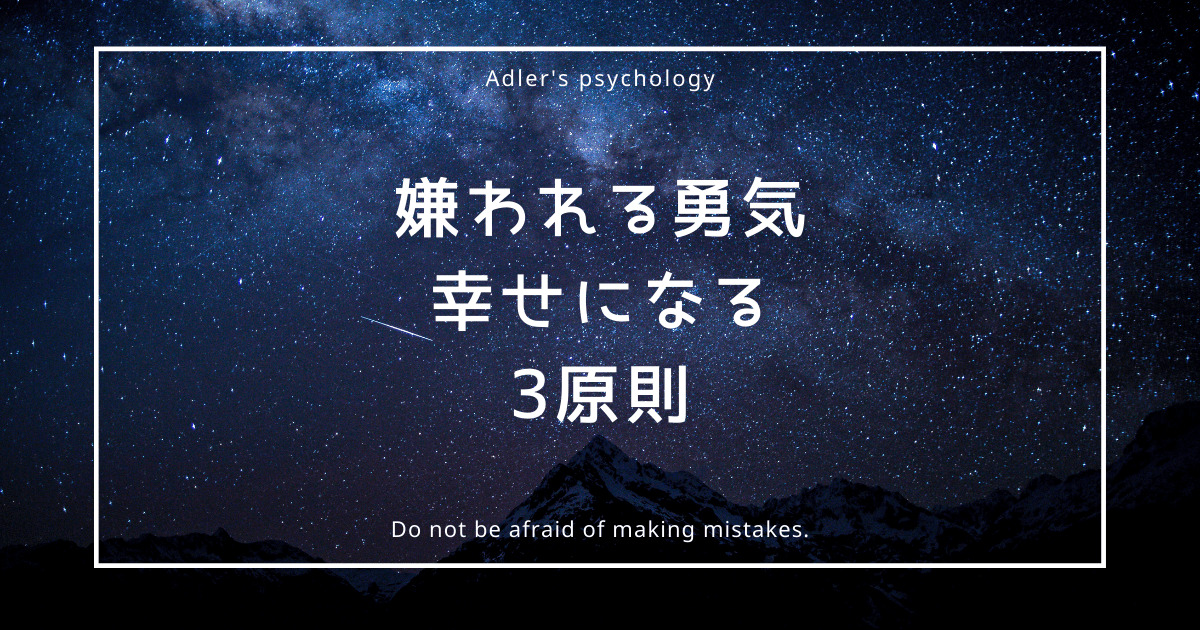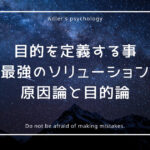人間の多くの悩みの原因は対人関係であり、他者との関わり方から生まれます。
残念なことに、世の中には「おかしな人」や「おかしな事」が多々あります。
変な人やヤバイ人とでさえ「分かりあえる、認められたい」など、こう言った相手にまで「嫌われないように」と気を使い続ける生き方は、不自由でしかありません。
こういった不毛な悩みから解放されるには「嫌われる勇気」が必要です。この考え方は、アルフレッド・アドラーの提唱する「個人心理学」に基づいています。
アルフレッド・アドラーは個人心理学を構築した人物で「自己啓発の父」と呼ばれ、人が幸せに生きるための指針を明確にしました。
以前書いた記事で「原因論と目的論」を書きましたが、書籍『嫌われる勇気』の中では、他にも幸せに生きるための三つの原則が示されています。
- 承認欲求に振り回されない
- 人生は競争ではない他者は競争相手ではなく仲間である
- 共同体感覚を持つ
アドラーが提言する考え方自体は非常に単純で、目的を達成するための考え方と自己肯定感を養う事を推奨しています。
そしてこの自己肯定と、承認欲求の否定を考える上で大切なファクターになる「幸せになるための3原則」こそが優れた心理的防御術だと私は考えています。
承認欲求に振り回されない
アドラー心理学で最も危険だと指摘されているのは「承認欲求」です。他者からの承認を強く求めることが幸福を遠ざけると指摘します。
「人間は本来、自分の価値を他人の期待や評価によって測る必要はありません」。
承認欲求を回避する事や、世間の評価を気にしなくするための方法としてアドラーが出した答えは「課題の分離」です。
これは成功者が無意識に実践しているもので、課題の分離とはその名の通り「自分の課題」と「他者の課題」を分けることです。
「自分が取り組むべきこと」と「他者が担うべきこと」を区別し、他人の評価や反応に過度に関わらないという姿勢です。
承認欲求に負けてしまうのはこの課題の分離が正しくできていないからです。
たとえば、自分が進学ではなく起業を選んだとして、その選択を親が認めるかどうかは親の課題であり、自分の課題ではありません。
自分の人生において出来るのは、自分が信じる最善の道を選ぶことだけであり、それについて他者がどのような評価を下すのか、承認するかは他者の課題でありどうする事も出来ません。
他人の課題に踏み込みすぎると、承認欲求に囚われやすくなります。自分の選択に責任を持ちつつ、他人の反応はその人の領域だと切り離すことが、心の自由につながる、と言うのがアドラーの答えです。
誰の課題なのかを明確に区別し、人の評価ではなく自分が信じる道を選ぶという自分の課題に集中することが重要です。
スティーブ・ジョブズがスタンフォード大学で行なった演説でも述べている通り、
承認欲求を満たすと言うのは他人から見た自分であって、自分自身の本当の欲求ではなく、自分の人生を歩んでいないと言う事を覚えておきましょう。
あなたの生きる時間は限られてる。だから、他人の人生を生きてはいけない。自分の人生の時間をムダにしてはいけない。
ドグマ(教義、常識、既存の理論)にとらわれるな。それは他人の考えた結果で生きていることなのだから。
他人の意見が、雑音のようにあなたの内面の声をかき消したりすることのないようにしなさい。
最も重要なのは、自分の心と直感に従う勇気を持ちなさい。
あなたが本当にどうなりたいのか、自分の心が既に知っている。だから、それ以外のことはすべて二の次だ。
——スティーブ・ジョブズ Steven Paul "Steve" Jobs
人生は競争ではない他者は仲間である
人間関係を「勝ち負け」で捉えると、常に優位であろうとし、劣等感や優越感に振り回されます。
他人の幸せや成功を妬んだり、失敗した人を見て喜んだりする心理状態は極めて不健全であり、「人の成功は自分の負け、人の失敗は自分の勝ち」だと感じるようになります。
こうした関係は孤立を生み、他人の成功を喜べなくなります。
アドラーは、健全な劣等感とは「他者との比較」ではなく「理想の自分との比較」から生まれると述べています。
成長の基準を自分の内側に置くことで、他者との不毛な競争から解放されます。
自分が「こうありたい」と思う姿を明確にし、それを基準に日々行動することが、長期的な充実感を生みます。
ポイントは目指す対象や比較対象比は他人ではなく「理想の自分」とする事です。
これを指し示す言葉としてアドラーは下記の言葉を残しています。
「健全な劣等感とは他者との比較ではなく、理想の自分との比較から生まれるものだ」
この話は目的論の最たるものなので、目的論の内容を見るとより頭に入ると思います。
-

-
参考目的を定義する事が最強のソリューション!原因論と目的論
問題が起こった時に、当事者を強く積める人は何処にでもいるのではないでしょうか? 問題が起きた時に現状を理解したいという気持ちはわかりますが、「原因を理解する」事と「相手を責める」事は全く別問題です。 ...
周りの人との比較ではなく、自分自身がどうなりたいのかという明確な目的を持ち、どうなりたいか決まったのなら、既にそうなっているかのように行動しましょう。
イメージと行動をセットにして行動しましょう。
共同体感覚を得る
アドラー心理学でいう「共同体感覚」とは、自分が社会や周囲の人々の中で価値ある存在であると感じられる状態です。
これは「承認されたい」という欲求とは異なり、「貢献できている」という実感から生まれます。
そのために重要なのが次の3つです。
自己受容:自分の短所や限界を含め、ありのままを受け入れること。
他者信頼:見返りを前提とせず、まずは信頼する姿勢を持つこと。
他者貢献:感謝や評価を目的とせず、純粋に相手のためになる行動を取ること。
これらを実践することで、「自分はここにいていい」という所属感が生まれ、精神的な「幸福」や安定が得られます。
自己受容
自己受容とは「肯定的な諦め」と言われ、あるがままの自分を受け入れ、変化に順応し進んで行くことです。
大切なのは生まれ持った才気を考えるのではなく、与えられた手札をどう使うかと言う事です。
自分を偽らずに、ありのままを受け入れ自己肯定をしていきましょう。
他者信頼
ギブアンドテイクのある関係ではなく、無条件の信頼を前提にしている事こそ深い関係が築けるようになります。
対人関係においては信じることを優先し、他者を仲間とします。
ここで課題の分離が活きてきます!相手が裏切るかどうかは相手の課題なので、自分は無条件で信じることによって深い関係が生まれます。
信頼していない事を相手に悟られては、前向きな関係が築くのは不可能です。
他人は敵ではなく、仲間だと享受できれば「ここにいてもいい」という所属感が育まれます。
そして他者信頼の考えは自己受容から生まれるているのです。
他者貢献
「他者貢献」は人に感謝されるために人に貢献しようとすることですが、自己犠牲ではありません。
周りから何か見返りを求めて行う貢献は偽善です。
周りが仲間でその人に何かできないだろうか?という純粋な行動は幸福感につながります。
こういった実践から共同体感覚が得られ、それがありのままの自分を受け入れる自己受容につながるのです。
人に貢献できていると感じることが、自分の価値であり幸せにつながるというのがアドラーの考えです。
人の手助けをして、相手の心の底から「ありがとう」と言われた時に感じる気持ちが幸せの答えです。
まとめ
アドラー心理学の三原則は、他者の評価や競争から自由になり、自己実現と社会的つながりを両立させるための指針です。
幸せになるには目的に対してどう進めばいいかを考え、障害を越えていく考え方といえます。
承認欲求を満たす人生は不幸になる
人生は競争ではない他者は仲間である
共同体感覚を得るために行動する
他者に与える傾向にあるギバーという性質を持っている人の方が、社会的に成功しやすいという結果が出ていることから、成功者の多くがアドラーの三原則と一致しているのは偶然ではないでしょう。
忘れてはいけないのが、アドラー心理学や嫌われる勇気を読んだだけではあまり意味がありません。
アドラー心理学と言うのはあくまで思想なので、読んで共感するだけではなんの意味もないのです。
なので、日々の小さな行動の中で、出来る事から実践して行きましょう。