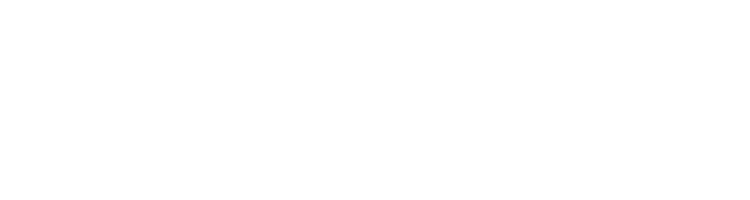人生の節目や環境の変化により、就寝時間が変わることは珍しくありません。
転職や出産、健康状態などの変化を経験する中で、「今の自分の睡眠習慣は周囲と比べてどうなのか」と気になったことはありませんか?
そんな疑問に答えるかのように、アメリカ人の睡眠習慣に関する興味深い調査が行われました。
調査では、平均的な就寝時間、睡眠準備の開始時刻、布団に入るまでの所要時間、夜更かしを後悔する頻度、さらには夜更かしの理由までが明らかになっています。
この結果を踏まえ、睡眠と神経多様性に精通する英国UKCP認定心理療法士であり、『How to Be Awake』の著者ヘザー・ダーウォール=スミス氏へのインタビューも交えながら、「理想的な就寝時間とは何か」「睡眠の規則性が持つ健康への影響」「安定した睡眠サイクルを作る方法」など、眠りの質に関わるさまざまな観点を解説します。
調査の概要|アメリカ人の平均的な睡眠パターン

Avocado Green Mattress社の依頼で実施された、2,000人を対象とした調査によると、多くの人が夜10時15分に就寝準備を開始し、10時36分には布団に入ります。
つまり、眠りにつくまでに平均21分の準備時間があることがわかります。
実際に眠りにつく時間は平均11時18分。ベッドに入ってから眠るまでには約40分の時間差があります。これは、現代人がリラックスし入眠に至るまでに一定の時間を要することを示しています。
さらに、回答者の多くは週に3回ほど「もっと早く寝ればよかった」と後悔していることが判明しました。
夜更かしの理由としては、29%が家事や雑務、21%が夜を好む性格、15%が仕事の始まりを先延ばししたい気持ち、13%がパートナーとの貴重な時間を過ごすためと答えています。
パートナーと同じベッドで寝ている人は46%で、そのうち49%が「一緒に寝るとよく眠れる」と回答。反対に14%は「眠りが悪くなる」と答え、その原因の63%が「パートナーのいびき」でした。
理想的な就寝時間

もし11時18分という平均的な就寝時間に、遅すぎると驚いたなら、あなたが「朝型人間(ラーク)」である可能性があります。
逆に早すぎると感じたなら「夜型人間(オウル)」かもしれません。
- 朝型(ラーク):体内時計が早く動く傾向があり、9時〜11時が理想の就寝時間。早寝早起きが自然に合う。
- 夜型(オウル):遅い時間に眠くなり、0時〜2時が理想の就寝時間。夜に活動的になる傾向がある。
「正しい就寝時間」とは、自分自身の体内時計=クロノタイプに合わせることが大切なのです。
ただし、午前0時30分を過ぎてから寝ることが常習化すると、健康リスクが高まることが研究で示されています。
Health Data Science誌に掲載された研究では、88,461人の成人の睡眠データを解析した結果、深夜以降の就寝によって肝硬変のリスクが2.57倍、壊疽のリスクが2.61倍になることが判明しました。
「就寝時刻」よりも「睡眠の規則性」が重要

仮に理想的な就寝時間に届いていなくても心配する必要はありません。
専門家によれば、毎晩同じ時間に寝ることが、睡眠の質に大きく影響します。
体内時計(概日リズム)を安定させるためには、週の間で就寝時間の変動が30分以内であることが望ましいとされています。
この安定性により、深く回復力のある睡眠を得ることができ、体調や精神状態にも良い影響をもたらします。
ダーウォール=スミス氏は、「就寝時間を一定に保つことで、体が『そろそろ眠る時間だ』と学習し、質の高い睡眠が得られる」と述べています。
実際、睡眠の不規則性は「社会的時差ぼけ」と呼ばれ、肥満や心臓病などのリスク要因にもなりえます。
さらに、睡眠の規則性が高い人は、死亡率が最大48%も低下する可能性があるという報告もあります。
安定した睡眠スケジュールを維持するためのポイント

- 自分に合った就寝時間を見極める :自然に眠くなる時間や、目覚ましを使わずに起きられる時間を観察し、自分のリズムを把握しましょう。Munich Chronotype Questionnaireなどのオンライン診断も活用できます。
- 毎日同じ時間に起きる :前日に夜更かししても、起床時間は固定することが重要です。これによりメラトニン(眠気を誘うホルモン)のリズムが安定し、翌晩の入眠がスムーズになります。体は「睡眠アーキテクチャ」を調整し、不足した眠りを補う力を持っているため、一晩の失敗で過度に心配する必要はありません。
- ナイトルーティンを整える :就寝前の習慣も睡眠の質に影響します。読書、入浴、瞑想など、穏やかで予測可能な行動を取り入れ、心身をリラックスさせましょう。これは「睡眠衛生」と呼ばれ、脳を「この習慣=眠る時間」と認識させることで、より安定した睡眠を実現します。
質の高い睡眠は、習慣づくりと自己理解から始まります。自分のリズムに合った規則正しい生活を意識しましょう。